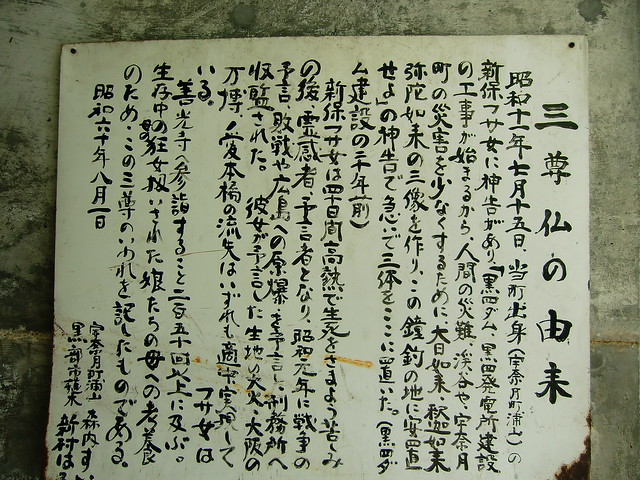御厨子神社の月輪石
御厨子神社境内に鎮座。
饅頭型の巨石の中心を、斜めからスライスしたような亀裂が印象に残る。この亀裂と直交するかのように異なる石質の層が直線状に走っているのにも注目したい。
手前に注連縄と紙四手が飾られ神聖視されていることはうかがえるが、情報収集不足もあり来歴は不明。

月輪石

月輪石近景
御厨子山妙法寺の光明不動
妙法寺の入口路傍に岩肌を見せる小さな自然石。
この岩肌に不動明王の姿が見えれば眼病が治るといわれる。

光明不動
天香山神社
天香久山の北麓に鎮座し、山をまつる神社と考えられる。
本殿背後の斜面から岩肌が露出しており、これが社殿建築以前の祭祀の場だったという説もあるが定かではない。

天香久山(フグリ山から望む)

天香山神社

天香山神社本殿背後の岩肌
天岩戸神社
天香久山の南麓に鎮座。
天照大神が日本神話の岩戸隠れを行なったと伝えられる場所で、拝殿の裏に4体の岩の集積があって岩室状の空間を形成している。これを天岩戸としてまつっている。
玉垣内に真竹が自生し、毎年7本ずつ生え変わることから「七本竹」と呼んでいる。

天岩戸
天香久山の「月の誕生石」と「蛇つなぎ石」
未訪。天香久山の山中にあるらしい。
「月の誕生石」は月を産んだ岩石といい、その産湯と足跡が岩石に残るという特異な由来を持つ。
「蛇つなぎ石」は岩肌に蛇が巻きついているかのような石のシワが残るという。
豊浦の立石
飛鳥には「立石」と呼ばれるものがあり、豊浦・小原・岡・川原・上居・立部の6ヶ所に散在している。
その内の1つ、豊浦の立石は甘樫坐神社の境内に残る。
甘樫坐神社は『日本書紀』印恭天皇条で明神探湯が行なわれた場所に比定されており、その故事を模して現在は立石の前で4月に明神探湯神事が行なわれている。甘樫の神を立石に擬して、神である立石の前で神事を行なうという構造と解される。
ただ、元来の立石の役割については不明であり、一般的には飛鳥京の条理の地割り石だったという説や、寺域を示していたなどといわれている。

豊浦の立石。手前は明神探湯神事に使う炉。
須弥山石・石人像
斉明天皇期の漏刻台(水時計台)とされる水落遺跡のすぐ近くから出土した石造物。現在は飛鳥資料館の館内に移設展示されている。
須弥山石・石人像ともに内部に導水構造を有し、配水施設と組み合わせれば石像から噴水が出る構造となっている。
『日本書紀』に斉明天皇が須弥山石のもとで饗宴を催したという記述があり、これに該当するのではないかと考えられている。

須弥山石(飛鳥資料館レプリカ)
弥勒石
入鹿の首塚の南に位置。胴体はずんぐりと長く屹立し、目鼻立ちは摩滅してしまっているがしっかりとした頭部を持つ石造物。
弥勒石という響きとは裏腹の素朴な造形であるが、現在でも供え物が絶えず信仰されている。下半身の病に霊験ありという。

弥勒石
飛鳥坐神社の立石群
飛鳥坐神社は鳥形山という小山の上に鎮座する。大字は「飛鳥」、小字は「神奈備」。
境内そこかしこに棒状の立石が安置されている。陽石が参道に一直線に並び続けている。

むすびの神石
むすびの神石は、陽石と陰石が一対になって並んでいる。陽石ばかりのこの神社において、陰石を要する珍しい例である。

奥の大石
「奥の大石」は、奥社の中にある。高皇産霊神が宿る霊石とされている。
小原の立石
前述の通り、飛鳥の立石群の1つとして伝えられているが、現在は場所が特定できず行方不明という。
亀形石造物
2000年の発掘調査による出土で一躍有名になった飛鳥の石造物のニューフェイス。
斉明天皇期の遺跡と考えられ、亀形石造物とその手前に接する小判形石造物を中心に、その周囲から敷石遺構、配水遺構などが見つかった。
石造物自体も水を溜め込み次に導水するという配置構造を持っていることから、『日本書紀』において斉明天皇が手がけた石造工事の遺跡だというのが大方の見方となっている。

亀形石造物
岡の酒船石
飛鳥の謎の石造物の代表格として知られる。
石の表面に円形の窪みと直線状の溝が幾何学的に配置された造形物で、石の左右端は削り取られているため完全な形は分からなくなっている。その用途を巡っては、窪みに酒を流し込んでいたとか、何らかの液体の調合装置だったとか、地図や天文台説も唱えられ、古くから諸説入り乱れた。
2000年に上述の亀形石造物が出土。酒船石周囲の山腹斜面からも石垣遺構などが発見され、亀形石造物と酒船石をつなぐ石造の水路のような遺構も見つかったことから、酒船石と亀形石造物を含む周辺一帯が大規模な導水施設として機能していたのではないかという説が有力になっている。
しかしこの導水施設がどのような目的に基づいて築かれたものだったのかについては結論が出ていない。水あるいは液体を流すための造形ということは分かったが、鑑賞対象としての庭園だったのか、宴の場だったのか、祭祀の要素も入っていたのか、それとも実用的な用途に使われていたのか、製作者の意図まではまだ読めていない。

岡の酒船石
出水の酒船石
岡の酒船石と類似した溝を持つ石造物。
実物は京都市南禅寺の碧雲荘に運ばれているが、レプリカを飛鳥資料館で見ることができる。
川原の立石
出水の酒船石から飛鳥川を挟んだ向い側に存在。
現在は地中に埋められている。
岡寺奥の院彌勒堂
日本最大の塑像である如意輪観音を本尊とし、663年に草壁皇子の住んでいた岡の宮を仏寺にしたのが始まりという。
奥の院彌勒堂は石窟になっており弥勒仏をまつっている。石仏のほかにも仏足石・板碑など数多くの石造物を見ることができる。

奥の院(写真中央)
岡の立石
未訪。岡寺仁王門の北から細い山道を登っていくと高さ約3mの立石があるという。
上居の立石
石舞台古墳から東の車道沿いにあり分かりやすい。高さ1.9m。

上居の立石
マラ石
マラ石という名前から性石信仰の名残と見る立場もあるが、マラ石という命名は考古学者の石田茂作によるものとされ、やや誘導的な名称と言える。他の立石と同様、京域・寺域の標石ではないかという見方も可能だろう。
飛鳥川を挟んだ対岸にフグリ山(ミワ山)があり、マラ石がこの山を方向に傾いて立っていることから両者の関連を述べる向きもあるが、マラ石は元来直立していたとの説もある。

マラ石
フグリ山/ミワ山
石舞台古墳の南方にそびえる丘陵をフグリ山あるいはミワ山と呼ぶ。
山頂尾根上に岩石の露頭が群集し、神聖視されていた磐座ではないかという説があるが、そのことを裏付ける歴史資料に欠け真相は不明。

フグリ山/ミワ山(北東から撮影)

山頂尾根の露岩群

露岩群の一部
くつな石
昔、ある石屋がこの石にノミを一打ちしたところ赤い血が噴出し、傷ついた蛇が現れたので、石屋は恐ろしくなって逃げ帰った。しかしその夜から熱と腹痛に冒され、やがて亡くなってしまった。村人は神の祟りだと畏れ、この岩石を神の宿る石としてまつったという。
伝承の内容から、これは磐座ではなく石神の事例である。山の斜面から板状の石がせり出しており、大きさ自体は人の背丈ほどで目を引く規模ではない。伝承を信じると信仰の開始時期は後代に下るようだが、立地は山腹谷間川沿いであり、伝承にも蛇が登場するように水の信仰を想起させる場でもある。
くつな石の手前には鳥居が設けられ、川には小ぶりの滝の禊場が設けられているが、これらは後世に敷設されたもの。

くつな石
橘寺(二面石・三光石)
聖徳太子の生誕伝承地。
二面石は、高さ1mほどの石の裏表両面に顔が彫られている。人間の善悪両面を石に表現したものだと説明されている。
三光石は、3つの石が凝り固まったかのような形をしている。伝承では聖徳太子が経講を行なった際、この石が光輝き、日の光、月の光、星の光が放たれたといわれる。
聖徳太子の神聖な足跡を今に伝える働きを持った岩石である。

二面石

三光石
立部の立石
未訪。定林寺跡にあり、立石というが地表からちょっと顔を出す程度の岩石だという。
亀石
前方部に目・鼻・口が付いて、後ろは甲羅みたいな物が盛り上がって彫られている。亀の形状を模したものとされるが、一説によると甲羅の部分に羽の様な物が付いていたという話もある。
昔、川原のナマズと当麻のヘビが大和湖を巡って争いがあり、ナマズが負けて湖の水はヘビに取られてしまったので、川原にいた亀が枯死してしまった。これを哀れに思った村人が供養のために作ったのが亀石という。
亀石はかつて東を向いていたというが、少しずつ西に向いていっているといわれる。現在南西を向いているが、西の当麻方向を向いた時には大和一帯が泥の海になると言い伝えられている。
現状では祭祀に用いられてはいないが、伝承の中では供養祭祀のための装置として用いられており、岩石祭祀の事例と言える。

亀石
鬼の俎と鬼の雪隠/鬼の厠
道行く人々を鬼が襲い、俎で捕食しその後雪隠で用を足したとの伝説がある。恐れられるべき存在ではあるが、その災禍を鎮めるような祭祀は行なわれておらず、岩石祭祀の事例とまでは言えない。
昔は何の用途のものだったか謎だったが、現在では横穴式石槨の底石(俎)と蓋石(雪隠)だったことが判明し、天武・持統天皇期の型式であるとされている。

鬼の俎

鬼の雪隠/鬼の厠
猿石
欽明天皇陵に隣接して吉備姫王墓という古墳がある。宮内庁管理のため玉垣が設けられており、その玉垣内に猿石と総称される4体の石造物がある。
正面向かって左から「女」「山王権現」「僧」「男」という名称が付けられており、これらは元禄2年(1702年)に田んぼの中から見つかり、明治時代になって現在地に移設されたという経歴を持つ。
猿を彫刻したとも異国人の風貌であるとも、韓国済州島のトルハルバンやサイパンにある石像が猿石と似ているともいわれる。

「女」と「山王権現」

「僧」と「男」
高取の猿石
未訪。高取城の登山道途中にある。前述の猿石4体と同時に出土したという話がある。

高取の猿石(飛鳥資料館レプリカ)
益田の岩船
飛鳥の石造物の中でも最も巨大なスケールを誇る。
住宅団地(橿原ニュータウン)の突き当たりの丘陵にあり、急な山道を5分ほど登ると高さ5~6m、総重量900tに達するという岩船がある。付近には露岩の存在が見当たらないことから、これは人工的に運搬されてきたものであるともいわれているが、その巨大さと立地の急峻さからにわかには信じがたい。
石の表面にはまるでタイルを貼り付けたかのような格子状の彫刻があり、頂面には2つの方形穴とそれをつなぐ浅い直線の彫りが見られる。この頂面を横倒しにすると、2つの横口式石槨の形状となることから古墳石室石材説が有力であるが、定説には至っていない。

益田の岩船。寄りかかっている大木と比較してその巨大さが分かる。
人頭石
現在、広永寺境内に手水石として存在。
独特な風貌を持ち、猿石と同時に見つかったものともいわれているが詳細は分からなくなっている。

人頭石(飛鳥資料館レプリカ)
天津石門別神社
かつて九頭神社/九頭明神/九頭龍明神などと呼ばれていたが、『延喜式神名帳』記載の天津石門別神社に比定され以後社名を現在のものとした。
本殿は木造建築物ではなく、榊の周りを板石で囲んでそれを祭祀対象としたもの。榊を神霊の宿る神籬とし、周囲の板石はまさに磐境と呼べる役割を負っている。時代は不明だが、磐境祭祀の実例と認められる。

天津石門別神社

基壇の上にさらに板石が榊を囲んでいる。